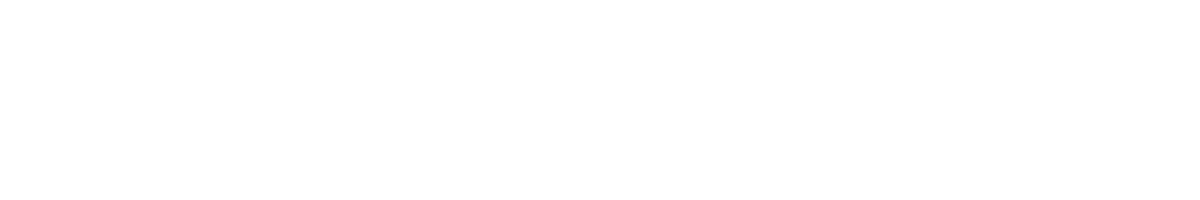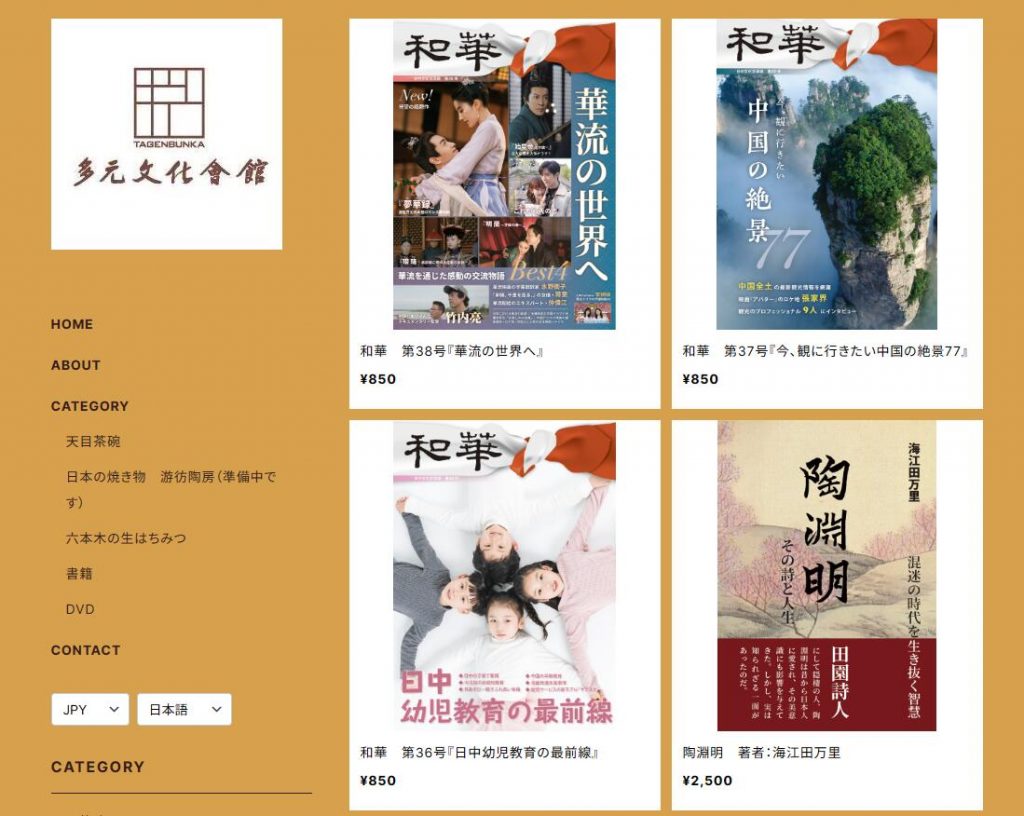中国史劇を彩る装飾品:鳥の数で身分を分ける「翟冠」②
前回に引き続き、「翟冠(てきかん)」に用いられている代表的な工芸について深掘りしていきます。
挑牌(ちょうはい)
挑牌は、金製の飾り簪(かざりかんざし)と房飾り(流蘇〈るす〉)の二つの部分から構成されており、主に鳳冠(ほうかん)や翟冠(てきかん)の装飾として使われます。これは格式の高さを示すものです。簪の部分は、鳳凰や龍、蓮の花など、象徴的な意匠をかたどったものが多く見られます。房飾りは真珠を編んで作られ、四角形や透かし模様の形に仕立てられています。さらに、その上には宝石がちりばめられ、いっそうの華やかさが加えられています。
花樹(かじゅ/花飾り)
花樹とは、鍍金(ときん)や真珠、翠玉(すいぎょく)などの素材で作られた花の飾りで、宝石による装飾が施されています。柄の部分はバネ状になっており、一本だけでなく複数が使われるのが一般的です。『宋史・輿服志』には「皇后の髪飾りには花が十二株ある」との記述があり、皇后の鳳冠の形についての記録となっています。これは隋や唐の制度を受け継ぎつつ、冠の上に「九龍四鳳(九匹の龍と四羽の鳳凰を組み合わせたもの)」の装飾が加えられていることを示しています。
鳳冠と翟冠の違い
鳳冠と翟冠の主な違いは、着用する人物の身分によって定められています。史料によりますと、皇后や皇太妃が着用するものが「鳳冠」と呼ばれ、親王の妃や妃嬪、またはそれ以下の官僚の妻が着用するものが「翟冠」とされています。制度上では、親王妃・皇妃・公主が使用するものも翟冠に分類されますが、その上に吊るす簪には金の鳳凰が用いられます。一方、郡王妃以下の官位の者の妻が使用する冠では、金の翟(てき)があしらわれています。
僭越の現象
明代の制度では、鳳冠の着用は皇后および皇太妃のみに許されており、それ以外の者が私的に使用することは基本的に禁止されていました。しかし、実際には明代の中後期になると、鳳冠は高官や富裕層の間で地位や財力を誇示する手段となっていました。『天水冰山録』*1には、嘉靖年間の宰相・厳嵩(げんすう)の家に十数点の鳳冠があったと記されており、「五鳳の真珠冠が六つ、重さは九十三両、三鳳の真珠冠が七つ、重さは五十三両一銭」といった詳細な記録も残されています。
*1『天水冰山録(てんすいひょうざんろく)』:明代の権臣・厳嵩(1480–1567)とその一族が失脚・抄家された際に没収された膨大な財産を記録した目録。
江蘇人民出版社『天上取様人間織ー≪玉楼春≫里的服飾之美ー』より一部引用(筆者翻訳)
前回記事:鳥の数で身分を分ける「翟冠」①」はこちら
関連記事:「中国史劇を彩る装飾品:「鳳冠」に宿る数多の伝統技術」はこちら